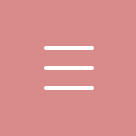睡眠時無呼吸症候群
ページ内のコンテンツ一覧
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は睡眠中に頻回に呼吸が止まる、浅くなるために、ぐっすり眠ることができない病気です。大きないびきや夜間の呼吸停止、起床時の頭痛、日中の強い眠気、集中力の低下などの症状があります。
呼吸が止まると、体に酸素が行き渡りません。そのため睡眠の質が低下しますし、心臓や脳に負担がかかりますので、放置すると高血圧、脳卒中、虚血性心疾患などの生活習慣病のリスクであることが近年明らかにされてきました。
また日中の眠気などのために仕事中に居眠りをして仕事に支障をきたす、居眠り運転による交通事故の発生など、社会生活に重大な影響を引き起こします。
このように個人の健康問題に限らず、社会全体の安全にも影響する睡眠時無呼吸症候群(SAS)ですが、その軽症以上の潜在患者は人口の約18%、中等症以上の潜在患者は約7%といわれています。
しかしながら、治療法が確立されているため、適切に検査・治療を行えば決して怖い病気ではありません。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?
睡眠中に頻回に呼吸が止まる、浅くなる疾患
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の問題
高血圧、脳卒中、虚血性心疾患、昼間の居眠り、居眠り運転による交通事故の発生
SASの定義について
睡眠中に10秒以上呼吸が止まることを『(睡眠時)無呼吸』といいます。検査機器では、持続時間が10秒以上、かつ呼吸センサーの振幅がベースラインから90%以上低下したことで判断します。
呼吸が浅くなることを『低呼吸』といいます。検査機器では、持続時間が10秒以上、かつ30%以上の気流低下(呼吸センサーの振幅がベースラインから30%以上低下)、かつ血中酸素飽和度(SpO2)が3%以上低下したことで判断します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の定義は、一晩(7時間)の睡眠中に10秒以上の無呼吸が30回以上起こるか、睡眠1時間当たりの無呼吸や低呼吸が5回以上の場合をいいます。
また睡眠時間1時間あたりの無呼吸数と低呼吸数の合計を『AHI』(無呼吸低呼吸指数)と呼び、この指数によって重症度を分類します。
| 無呼吸 | 睡眠中に10秒以上呼吸が止まること |
|---|---|
| 低呼吸 | 睡眠中に呼吸が浅くなること |
| AHI 無呼吸低呼吸指数 |
睡眠1時間当たりの無呼吸数と低呼吸数の合計 |
SASによる重症度分類
SAS(睡眠時無呼吸症候群)の重症度分類はAHI(無呼吸低呼吸指数)の数値を使用して行われます。
医学的には、AHI(無呼吸低呼吸指数)が5回以上~15回未満が軽症、15回以上~30回未満が中等症、30回以上が重症と分類されます。
日本の保険診療の仕組みでは、AHI(無呼吸低呼吸指数)が20回以上で保険適用となるため、医学的な診断と必ずしも一致していない現状もあります。
| 重症度分類 | AHI(無呼吸低呼吸指数) | 保険適応 |
|---|---|---|
| 軽症 | AHIが5回以上~15回未満 | (-) |
| 中等症 | AHIが15回以上~30回未満 | AHIが20回未満(-)、AHIが20回以上(+) |
| 重症 | AHIが30 回以上 | (+) |
SASの主な症状
十分に眠れないことが原因となって様々な症状が現れるようになります。 その症状には、周囲の方からいびきや無呼吸を指摘される、夜間の睡眠中によく目が覚める、起床時の頭痛や体のだるい感じがある、日中の強い眠気やだるい感じ、集中力の低下などを経験するなどの症状があります。
| 眠っている時 | いびきをかく 息が止まる 呼吸が乱れる 息が苦しくて目が覚める 何度も目が覚めて、トイレに行く |
|---|---|
| 日中、起きている時 | 強い眠気を感じる しばしば居眠りする 午前中に頭痛を感じる 記憶や集中力が低下する 全身倦怠感、疲れが取れない |
SASの種類
睡眠時無呼吸症候群(SAS)には閉塞性と中枢性の大きく2種類があり、多くは閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)です。閉塞性は、肥満や形態的な理由で上気道が塞がることで呼吸が停止します。中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)は、脳からの呼吸指令が正常に伝わらないことで起こります。両方を併せ持つ混合型もあります。
ページ内のコンテンツ一覧
SASの簡易検査とは
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の簡易検査では夜の睡眠中に、1時間あたりの無呼吸や、低呼吸(呼吸が浅くなる状態)の頻度を測定し診断していきます。 当院の呼吸器内科外来では機器を自宅に持ち帰り、自宅の寝室で検査ができる簡易検査を実施しております。
この検査では睡眠中の呼吸の状態、血液中の酸素飽和度などを同時に測定し、無呼吸や低呼吸の有無を知ることができます。 検査はご自宅で簡単に行うことができ、テープでセンサを張り付け、本体のボタンを押して検査をスタートさせ、いつもどおりお休みいただくだけです。 検査結果によって精密検査が必要となります。
記録項目
鼻 : 口鼻の気流、いびき音
指 : 血中酸素飽和度 など

簡易検査の結果とその方針
簡易検査では正確なAHI(1時間当たり)(無呼吸低呼吸指数)を測定することはできません。そこでAHIをREIと呼ぶことがあります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の簡易検査の結果でAHI(REI)(1時間当たり)(無呼吸低呼吸指数)が5回未満では正常と判断し保険治療は行えません。
AHI(REI)(無呼吸低呼吸指数)が5回以上から20回未満では睡眠時無呼吸症候群(SAS)は軽症から中等症疑いと診断し、
マウスピースが保険適応となります。
AHI(REI)(無呼吸低呼吸指数)が20回以上~40回未満では睡眠時無呼吸症候群(SAS)は中等症~重症疑いと診断し、要精密検査となります。
AHI(REI)(無呼吸低呼吸指数)が40回以上では睡眠時無呼吸症候群(SAS)は重症と判断しCPAP療法(持続陽圧呼吸療法)が保険適応となります。
簡易検査によるAHI(REI)の判定
| AHIが5回未満 | 正常 | (-) |
| AHIが5回以上~20回未満 | 軽症~中等症疑い | マウスピース、側臥位睡眠指導 |
| AHIが20回以上~40回未満 | 中等症~重症疑い | 要精密検査 |
| AHIが40回以上 | 重症 | CPAP療法 |
検査から治療の流れ
STEP01
医師からの問診とスクリーニング
STEP02
基本的な検査(自宅での簡易検査)
睡眠評価機器を用いて、自宅にて簡易検査をしていただきます。
確定診断(入院での精密検査)
STEP03
検査結果により治療法の決定
検査結果から、患者さまそれぞれの治療方法を提案します。
(例:CPAP療法、生活習慣の改善、マウスピース)
- 生活習慣の改善減量、横向きで寝る工夫、アルコールを控えるなど。
- 口腔内装置下あごを前方に固定することで、空気の通り道を開きます。
- 外科的手術気道閉塞の原因がアデノイドや扁桃肥大の場合等。
STEP04
治療の効果判定検査
判定検査について、説明文章が入ります。判定検査について、説明文章が入ります。
SASの精密検査とは
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断と治療方法を決定するための検査です。
当院の呼吸器内科外来では夕方から翌日朝までの1泊入院で検査ができる精密検査(PSG検査:睡眠時ポリソムノグラフィー)を実施しております。
身体にセンサーを装着(痛みはありません)した状態で一晩就寝いただきます。眠っている状態を調べる精密検査(PSG検査:睡眠時ポリソムノグラフィー)のため、1泊の入院が必要となります。
頭や胸・腹、足などに電極やセンサーを着けますが、痛みなどはありません。精密検査(PSG検査:睡眠時ポリソムノグラフィー)では睡眠中の呼吸や脳波・眼球運動、血液中の酸素飽和度、心電図、呼吸活動、手足の動きなど同時に測定し、睡眠の深さと質と呼吸の状態を調べます。
日頃ご家庭でお休みになるようにリラックスして検査をお受けいただきます。当院の検査機器はワイヤレスのため、自由に行動でき、一人でトイレに行くことも可能です。
お仕事を休まずに検査が可能ですので、サラリーマンや多忙な方に最適です。いびきや睡眠障害でお悩みの方はぜひご相談ください。
記録項目
眼の周り : 眼球運動
顎 : 顎の筋電図
鼻 : 口鼻の気流
喉 : いびき音
脳 : 脳波
腹 : 腹の動き
足 : 足の動き
胸 : 胸の動き、心電図
指 : 血中酸素飽和度 など

精密検査の結果とその方針
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の精密検査の結果で、AHI(1時間当たり)(無呼吸低呼吸指数)が5回未満では正常と判断され、保険診療は行えません。
AHI(無呼吸低呼吸指数)が5回以上から20回未満では軽症から中等症と判断され、マウスピースが保険適応となります。
AHI(無呼吸低呼吸指数)が20回以上では中等症から重症と診断し、CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)が保険適応となります。
精密検査によるAHIの判定
| 5回未満 | 正常 | (-) |
| 5回以上~15回未満 | 軽症 | マウスピース、側臥位睡眠指導 |
| 15回以上~20回未満 | 中等症 | マウスピース、側臥位睡眠指導 |
| 20回以上~30回未満 | 中等症 | CPAP療法 |
| 30回以上 | 重症 | CPAP療法 |
精密検査の流れ
17:00〜17:30
入院受付
オリエンテーション
18:30迄
シャワー
食事
18:30
検査準備
21:00
検査開始
5:00
検査終了
6:00
シャワー・更衣
退院
CPAP療法
CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)は、鼻より空気を送り、閉塞した上気道を押し広げることによって睡眠時の無呼吸を無くし、酸素不足を解消することができ、睡眠の質を向上することができます。
SAS(睡眠時無呼吸症候群)が招く高血圧症や狭心症、心筋梗塞といった循環器の病気など、合併症を予防することもできると言われています。
現在では、CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)は中等症以上の閉塞性SAS(睡眠時無呼吸症候群)に対する治療の第一選択として使用されています。
CPAPを使うと、ほとんどの患者さまが使ったその日からいびきをかかなくなり、朝はすっきり、昼間の眠気も軽くなり、消えることもあります。
重症のSAS(睡眠時無呼吸症候群)患者さまでは、CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)を使わなかった患者さまより長生きすることも分かっています。
- CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)は正しく継続的にご使用いただくことが大切です。
- 実際に使用する場合は説明を受け、取り扱い説明書をご覧ください。
閉塞性SASの治療CPAP療法とは?
CPAP療法とは持続陽圧呼吸療法で閉塞性SAS(睡眠時無呼吸症候群)の治療として第一に選択される呼吸療法です。
その他の治療法
睡眠時無呼吸症候群(SAS)のその他の治療法は、生活習慣の改善、口腔内装置(マウスピース)、外科的手術などがあります。
生活習慣の改善
減量、横向きで寝る工夫、アルコールを控えるなど。
口腔内装置(マウスピース)
下あごを前方に固定することで、空気の通り道を開きます。
※マウスピースの作成は当院の歯科で受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
外科的手術
気道閉塞の原因がアデノイドや扁桃肥大の場合など。